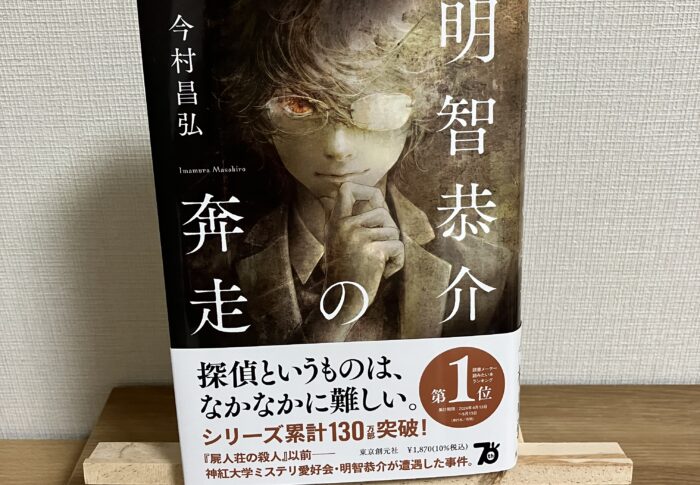過去の凶悪事件の呪いが令和の現代まで続いている!?中山七里『鬼の哭く里』
岡山県にある限界集落、姫野村。人口300人も満たないこの集落には、70年以上前から続く呪いが語り継がれていた。第二次世界大戦後に村人を6人惨殺した男が、今なお裏山にひそみ村人たちを狩り続けているというのだ。
村人が亡くなる日、裏山からは鬼の哭くような遠吠えが聞こえる。鬼の哭く夜は死人が出ると、まことしやかに語り継がれてきた。
そんな集落に、麻宮恭一という一人の男が東京から移住してきた。新型コロナウィルスでパニック状態のなか越してきたというのもあって、村人たちは彼に近寄ろうとはしない。中学生の裕也は赤いスポーツカーに乗っている麻宮が気になって、会話を交わす。普段、古くて狭い世界で生きている大人たちとしか会話しない裕也にとって、都会から来た麻宮との会話は知的で楽しいものだった。
麻宮は姫野村の呪いに興味を持ち始め、裕也に村人たちに話を聞いてくるよう頼んだり、郷土資料をあさったりし始める。村人たちは、余所者が我が物顔で村の中を歩き回るのを面白く思わない。そんななか、村の年寄りが死亡する事故が起こる。
コロナウィルスの風評被害と呪いの思い込みとが重なるように、物語は進んでいく。コロナにかかったのは都会から来た余所者のせい、年寄りが死んだのも都会から来た余所者のせいと、なんでもかんでも誰かのせいにしないとやっていられない閉鎖的な空間が見事に描かれている。全然理屈が通っていないのに、自分たちは正しくて余所者は正しくないと主張する人たちがリアルだった。
村人たちの新参者へのいじめは、実際に訴訟を起こしたところで大した額にはならず、投石などで故障した自動車の修理費を請求したところで、相手からお金を持っていない、払えないと言われてしまえば何にもならない。そのような麻宮の説明を聞いて、こういう閉鎖的なとこらからは逃げるしかないんだなと思ってしまった。
本書を読み終わった後、裕也が都会的な街に引っ越せますようにと願った。
中山七里さんの小説は、ミステリーで有名にも関わらず今回初めて読んだ。こういうどろどろした怖い話があったら他にも読んでみたい。